(※本記事は管理者の実体験に基づきますが、守秘義務およびプライバシー保護の観点から、特定の事業所や個人が特定されないよう一部を加工・配慮して執筆しています。)
はじめに:タイムカードと「15分の空白」
私が働いている居宅介護支援事業所では、特定事業所加算を算定しています。
その算定要件の一つである「毎週1回の会議」。今朝もその会議を行いましたが、今日の議題は事例検討ではありません。
「サービス残業の禁止」についてです。
きっかけは、労働基準監督署からの指摘でした。
「タイムカードの打刻時間と、実際の就業時間の間に15分以上の乖離(かいり)がある場合、それは残業とみなされる。」
その通達から、会社からは数か月分もの残業費の支払いがありました。
そして「今後は必要のない残業はしないように」と強い指示が出ました。
しかし、現場の実態はそう簡単には変わりません。
「仕事が終わらないのだから、残ってやるしかない」
職員たちはタイムカードを押した後、デスクに戻り、黙々と仕事を続けていました。
私自身、その状況を見て見ぬふりをしていました。
「みんな頑張っているから」と自分に言い訳をし、彼らの自主的な残業を「黙認」し、私だけ先に帰ることもありました。
しかし、その「黙認」こそが、職員を、そして事業所を危険に晒している。 そう痛感し、今朝の会議で、私は明確に禁止を伝えました。
なぜ帰れない? 膨大な「法定業務」と「減算」の恐怖
次の項目は「努力目標」ではありません。
一つでも欠ければ「運営基準違反」となる義務です。
【居宅介護支援事業所の必須業務(法定業務)】
- アセスメント(課題分析): 居宅を訪問し、生活状況や困りごとを聞き取る。
- ケアプラン作成: 自立支援のための計画を作成する。
- サービス担当者会議の開催: 本人、家族、関係者を含め会議を行いケアプランの合意を得る。
- 事業者との連絡・調整: サービス開始の手続きや調整を行う。
- モニタリング(実施状況の把握): 最低月1回は利用者の自宅を訪問し、面接・記録を行う。
- 給付管理業務: 毎月の国保連請求データ作成(ここが遅れると他事業所への入金も止まる)。
- 要介護認定の申請代行
- 関係機関との連携
- 記録の整備と保存: 完結の日から5年間の保存義務。
これらを全利用者に毎月、ミスなく行うだけでも膨大な時間がかかります。
しかし、私たちを精神的に追い詰めるのは、業務量そのものよりも、その背後にある「減算(報酬カット)」への恐怖です。
【たった一つのミスで報酬半減!? 減算の罠】
以下の業務に不備があれば、「運営基準減算」として、報酬が50%(半減)になります。
さらに状態が続けば、仕事をしていても報酬はゼロ(全額返還)です。
- モニタリング不実施・記録不備: 月1回の訪問、あるいは記録がないだけでアウトです。
- サービス担当者会議の不実施: 更新時や区分変更時に開催していなければ減算です。
- ケアプランの交付・同意の不備: 利用者や家族への説明、同意、文書交付の記録がなければ減算です。
さらに、
- 特定事業所集中減算: 特定の事業所への紹介率が80%を超えたら減算。(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与)
- 担当件数超過による減算: 1人の担当が44件を超えたら減算。居宅介護支援の依頼があって完璧な仕事を行っても減算になります。
たった1枚の記録漏れ、たった1回の訪問忘れが、事業所の経営を揺るがす大損害につながる。
このプレッシャーの中で、職員は「完璧に終わらせるまで怖くて帰れない」のです。
さらに積み上がる「加算要件」と「研修」の山
法定業務だけでも限界に近い状態で、特定事業所加算を算定している私たちの事業所には、さらに多くのタスクが課せられています。
【特定事業所加算の算定要件と終わりのない研修】
加算を取るためには、以下の項目を全てクリアしなければなりません。
※条件は他にもありますが今回は割愛致します。
- 毎週の定例会議: 利用者情報の伝達や留意事項の共有(週1回以上)。
- 他分野の研修会への参加: 障害者支援、ヤングケアラー対策、生活困窮者支援など、高齢者以外の分野の事例検討会への参加。
- 他法人との合同研修会: 自社だけでなく、他法人の事業所と共同での研修実施。
- 社内委員会、勉強会の開催: 計画的な研修の実施。
- BCP(事業継続計画)訓練
- ケアマネジメント実習への協力体制
そして極めつけが、「24時間連絡体制の確保」です。
夜間・休日問わず、利用者からの相談に対応できる体制を作ること。
この条件こそ、ケアマネジャーの私生活を一切顧みない、「行政の奴隷」とも言える過酷な要件です。
携帯電話を握りしめて眠る私生活に、私たちケアマネジャーは安らぎなどありません。
資格維持のための「更新研修」という理不尽
さらに私たちを追い詰めるのが、資格を維持するためだけの研修制度です。
全介護支援専門員は、5年毎に介護支援専門員更新研修を数日間受けなければなりません。
これを休むと資格を失職するため、どんな事情があろうと、たとえ体調が悪くても出席しなければなりません。
この更新研修がいかに現場を苦しめているか、以前詳しく書きましたので、ぜひこちらもご覧ください。
また、日中の業務時間は、これら以外の「予測不能な対応」で埋め尽くされていきます。
「何でも屋」化する現場:電球交換から救急車まで
必須業務に加え、私たちの時間を奪っていくのが、境界線のない「突発的な依頼」です。
行政や地域からは「何かあったらケアマネへ」と頼られ、現場では便利屋のような扱いを受けることもあります。
- 電球の交換や買い物の代行依頼
- 受診の送迎や付き添い
- 救急車への同乗要請
- 身寄りのない方の緊急対応、入院手続き
- 昼食時でもひっきりなしに鳴る電話
- 急な来客、ご家族からの呼び出し
これらに都度対応していると、本来やるべき書類業務を行う時間が、定時内には一分も残っていない。
それが日常です。
だから職員は、タイムカードを切った後に「サービス残業」をするしかない。 そう思い込んでしまっているのです。
業界の矛盾:「報われない」からこそ「自己犠牲」へ
そしてもう一つ、私たちを苦しめるのが、この業界特有の構造です。
介護報酬という公定価格で売り上げの上限が決まっており、どれだけ頑張っても給与には反映されにくい。 それなのに、経営側からは「件数を増やせ」というプレッシャーがかかる。
世間では賃上げのニュースが流れても、私たちの昇給は雀の涙ほど。
「本当に、やってられない」 そんな徒労感が現場を覆っています。
報われないからこそ、真面目な職員ほど「せめて仕事だけは完璧に」と、自分の身を削る(サービス残業をする)ことで責任を果たそうとしてしまうのです。
それでも「黙認」してはいけない4つの理由
しかし、どんなに同情すべき事情があっても、管理者がサービス残業を「黙認」することは許されません。
- 安全配慮義務違反のリスク
もし職員が過労で倒れた場合、「会社は長時間労働を知っていた(黙認していた)」として、損害賠償請求される可能性があります。 - 労働基準法違反(賃金未払い)
タイムカード打刻後でも、指揮命令下にあれば労働時間です。賃金を払わないのは違法です。 - 管理者自身の法的責任
「両罰規定」により、違反を放置した管理者個人も処罰の対象となります。 - 事業所運営のリスク
労基署の再調査や、特定事業所加算の取り消しなど、事業所の存続そのものが危うくなります。
職員の「心の声」と、管理者の「答え」
今朝の会議で禁止を伝えた時、職員たちの心の中には、反発の声があったはずです。

職員①
残業代はいりません。帰れと言われても、仕事が終わらないんです。終わらなければ自分の責任になる。だから勝手にやらせてください
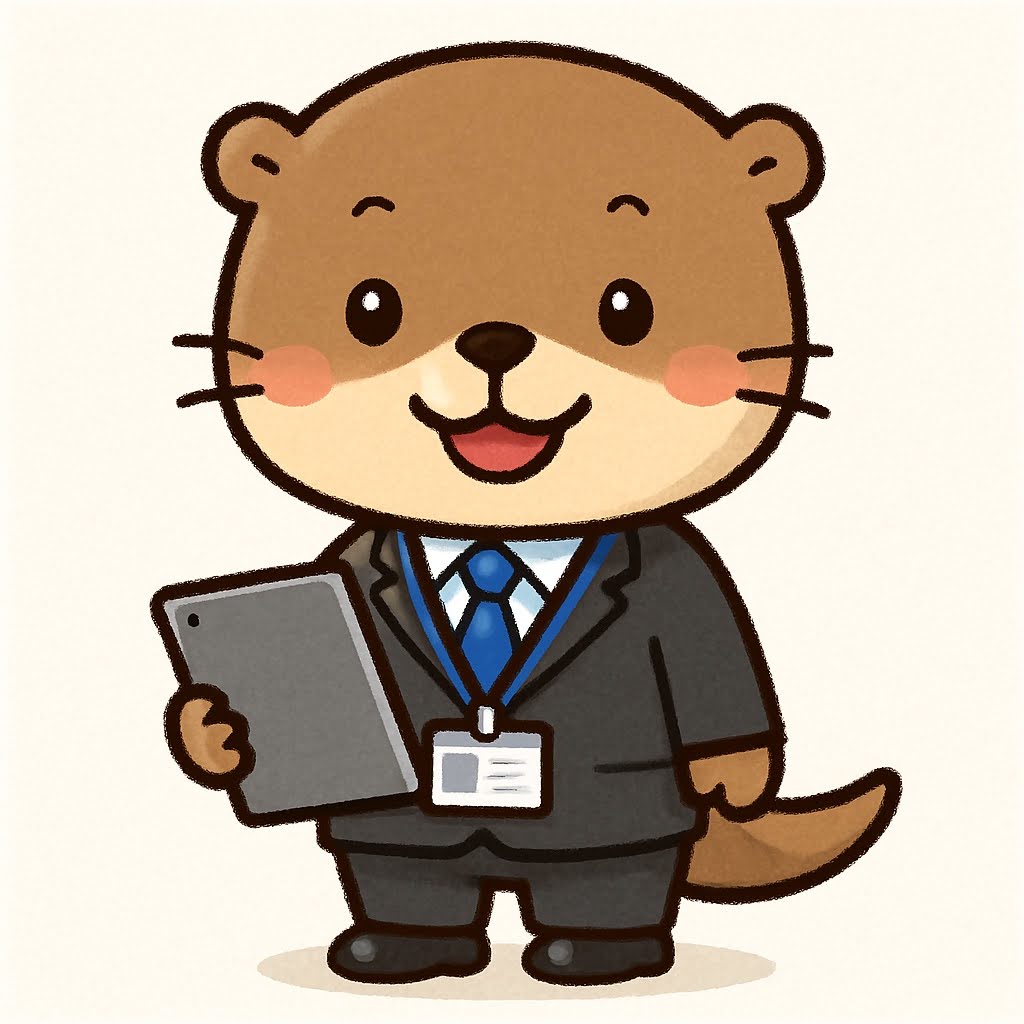
管理者まもる
「その責任感は痛いほどわかります。
しかし、『無給で働くこと』で解決しないでください。 あなたがサービス残業で業務を回してしまうと、『この業務量は適正だ』『この人数で回せる』という誤った実績が作られてしまいます。
それは結果として、会社への改善要求を遠ざけ、あなたの首を絞め続けることになります。」

職員②
管理者は先に帰っていいですよ。どうせ家に帰っても暇だし、今のうちに記録をさせてください
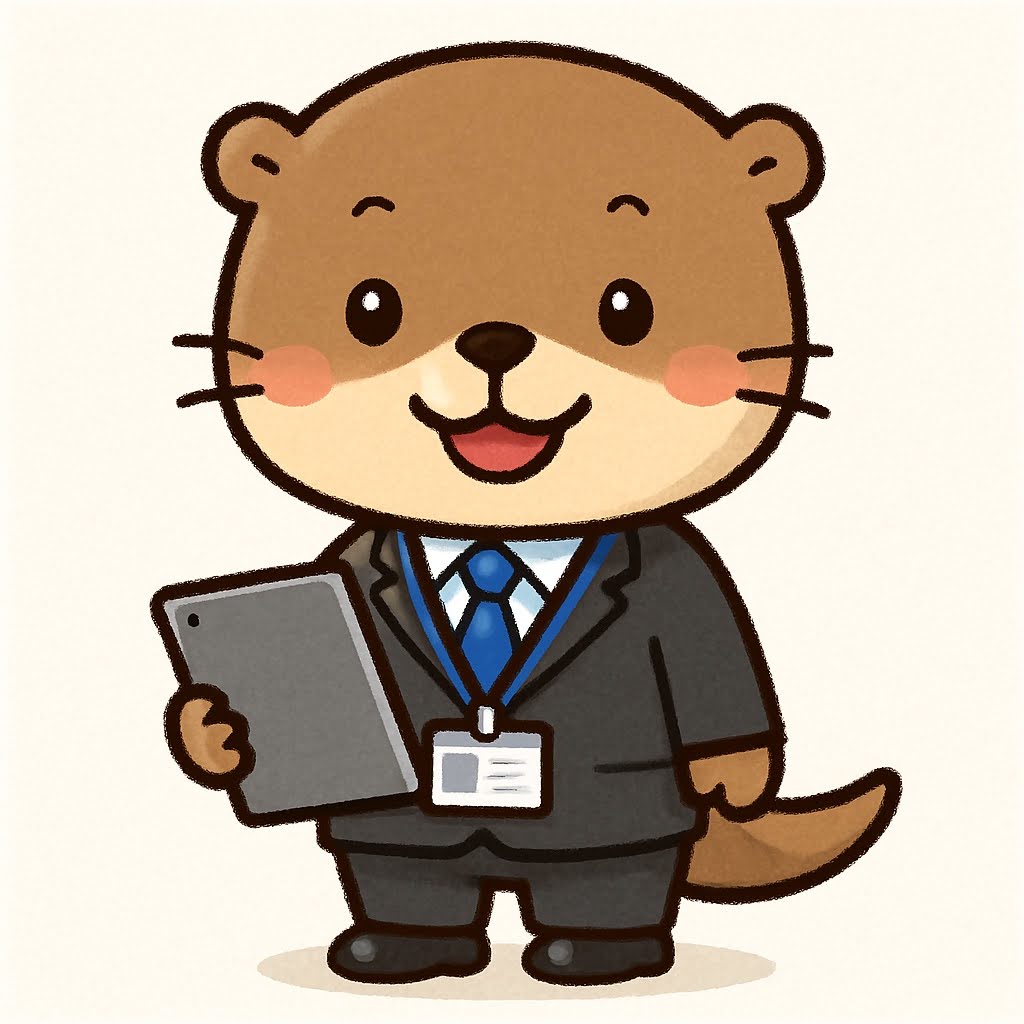
管理者まもる
『暇だから仕事をする』というのは一番危険です。
あなたの人生の時間を安売りしているのと同じです。 私が先に帰り、あなたが残る。その状態を『黙認』した瞬間、私は管理者としての職務を放棄し、法律違反の共犯者になります。
だからこそ、これからは申請のない残業は認めません。業務が終わらないなら、その原因を解決するために改善を図ります。
結論:「禁止」は、ケアマネジャーを「孤独な戦い」から守るため
私が今回、スタッフに対して「サービス残業の禁止」を明言したのは、単なるコンプライアンスのためだけではありません。
それは、ケアマネジャーという職業を、終わりのない孤独な戦いから守るためです。
この記事を読んでいる方なら、共感していただけるのではないでしょうか。
長くこの仕事をすればするほど、家に帰っても仕事のことが頭から離れず、リフレッシュできなくなっていく感覚。
ふとした瞬間に利用者の顔が浮かび、時には夢にまで仕事が出てくる。
真面目な人ほど、公私の境界線が曖昧になり、いつの間にか「24時間ケアマネジャー」になってしまいます。
しかし、意識的に「区切り」をつけなければ、心は休まる暇がありません。
一線を越え、心身をすり減らした先にあるのは、バーンアウト(燃え尽き症候群)です。
報われない業界構造の中で、たった一人でその重圧に耐え、誰にも評価されずに潰れていく。 私が一番恐れているのは、職員にそんな「孤独な戦い」をさせてしまうことです。
もちろん、「残業禁止」と号令をかけるだけで解決するほど、甘い現場ではありません。
「モニタリングの記録」などは、運営基準減算を防ぐためにも、絶対に削ることのできない必須業務です。
だからこそ、精神論ではなく、具体的な「業務改善」が必要です。
「必要な業務だから、サービス残業でカバーする」のではなく、 「必要な業務だからこそ、勤務時間内に終わらせるための優先順位と仕組みを、組織全体で考える」。
私の事業所では、これからの毎週の会議で、仕事量について定期的に話し合う事としました。
「あの時、サービス残業で乗り越えた」という過去の呪縛を断ち切り、 「あの時、チームの知恵と業務改善で乗り越えた」という新しい成功体験を作る。
もし、同じような苦しみの中にいる管理者の方、あるいはケアマネジャーの方がいるなら、どうか一人で抱え込まず、業務内容を思い切って変えるきっかけにしてほしいと願っています。
誰一人として孤独な戦いで燃え尽きさせないこと。
それこそが、私たち管理者に課せられた、本当の仕事なのだと思います。



