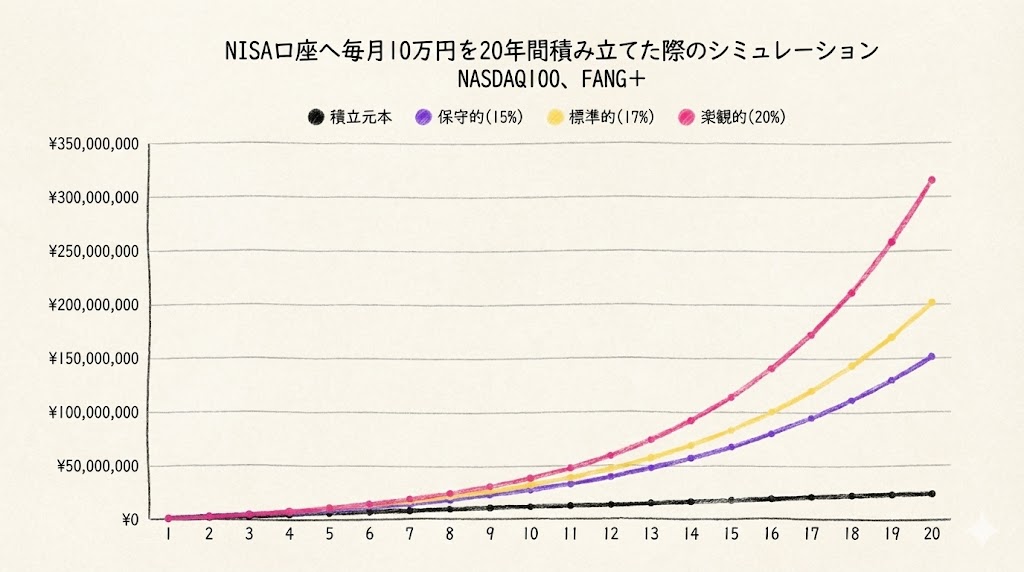はじめに
「介護の仕事」と聞くと、今でも「きつい、汚い、低賃金」といったネガティブなイメージを持つ方が多いかもしれません。
私がこの業界に入った時も、年配の男性から「男なのに介護職なんてやめろ」と何度も言われました。
しかし、そうした古いイメージとは裏腹に、介護は非常に専門性の高い、誇るべき仕事だと私は確信しています。
日々現場で汗を流す全ての介護職員の方々、そして利用者さんのために奔走するケアマネジャーの仲間たちを、私は心からリスペクトしています。
この仕事は「専門職」であり、知識と技術を磨くための確かなキャリアパスがあります。 代表的なものが「介護福祉士」、そして「介護支援専門員(ケアマネ)」です。
私自身も、介護職員として現場で働きながら必死に勉強し、ケアマネの資格を取得した過去があります。
そして今、私はその上位資格である「主任介護支援専門員(主任ケアマネ)」として、日々業務に向き合っています。
今日は、その「主任ケアマネ」とは一体何なのか。 そして、その専門性を証明するはずの資格を取得し、維持することが、現場の私たちにとってどれほど過酷な負担になっているか、そのリアルな声をお届けしたいと思います。
主任ケアマネ=管理者のための資格?
過去、介護職のキャリアパスは、「ヘルパー2級」から始まり「介護福祉士」、そして「介護支援専門員(ケアマネ)」へとステップアップしていくのが一般的でした。
現在はヘルパー2級が「介護職員初任者研修」に置き換えられており、「主任介護支援専門員」は、介護支援専門員の上位資格として位置づけられています。
では、この主任介護支援専門員は、何のために取る資格なのでしょうか。
単刀直入に言うと、これは「事業所の管理者になるために必要な資格」という側面が非常に強いです。
特定の事業所では、管理者を「主任ケアマネ」にすることが要件とされています。
そのため、現場では「管理者に選ばれたから、取りたくもない資格を取らされる」というケースも少なくありません。また取得しても給与は変わらない事業所もあると思われます。
(もちろん、高い志を持って取得される方も大勢いらっしゃり、手当をいただける事業所もあります!)
しかし、この資格、取るのも維持するのも、本当に大変なんです。
1. 取得の壁:70時間の研修と「無効化」の恐怖
まず、研修を受けるためのハードルが高いです。 「ケアマネとしての実務経験が原則5年以上」に加え、「地域のリーダー的役割を期待される人」でなければ、スタートラインにさえ立てません。
そして、研修そのものが過酷です。
私自身がこの主任介護支援専門員研修を受けた時は、合計で70時間にもおよぶ講習時間を費やしました。 もちろん、仕事をしながらです。 毎月の訪問や通常業務と並行してこの時間を割くのは、本当にすさまじい負担でした。
さらに、介護支援専門員に関する研修には、恐ろしい「決まり事」があります。
それは、体調不良などで一度でも講習を休めば、それまでの受講が全て無効(パー)になってしまうことです。
この時間的・精神的な負担の大きさから、仕事を続けられなくなったことを聞いたこともあります。
2. 維持の壁:高額な「自腹」費用と二重の負担
無事に主任ケアマネになっても、次は「資格の維持」という更なる壁が待っています。
驚愕の「自腹」が当たり前の世界
まず、更新研修を受けるために高額な費用がかかります。
※自治体により受講時間や費用は違います。
- 介護支援専門員 更新研修(5年ごと):約4万円~6万円
- 主任介護支援専門員 更新研修(5年ごと):約3万5千円~5万円
驚くことに、「主任ケアマネ」の資格を取っても、「ケアマネ」の更新研修は免除されません。
(※自治体によって運用は異なりますが、私は結果的に最初は5年間で3回も高額で長い研修を受けるハメになりました。)
私の自治体では、主任介護支援専門員の更新研修を受けた後は、介護支援専門員の更新も統一されて、5年間の有効期間となっています。
私自身は、職場の勤務(業務)として受講させていただき、費用も職場に負担してもらっています。
管理者として指名がなければ、最初に受ける方の殆どが実費での受講になることも想定されます。
さらに驚くべきことに、すでに業務に就いている方でも、貴重な有給休暇や休日を使って研修に参加し、この高額な費用を全額自腹で支払っている方も大勢いらっしゃるのです。
ケアマネの仕事をするために、どれだけの負担を個人に強いるのでしょうか。
3. 研修内容への絶望:「早く終われ」と祈るだけの時間
これだけの時間と費用(あるいは自腹)を払って、さぞかし有意義な研修が受けられるのだろう、と思うかもしれません。
しかし、私個人の感想としては、正直に申し上げて、この研修は苦痛でしかありませんでした。
内容は、ただひたすらグループワークばかりさせられるのです。 これは、主任介護支援専門員の更新研修本体だけでなく、その更新要件を満たすため(だけに)参加が求められる「年4回以上」の研修も、同様にグループワークばかりなのです。
私にとっては、何の成果も生まれません。ただ「早くこの時間が過ぎてくれ」と祈るだけの時間でした。
はっきり言って、職場でいつものカンファレンス(会議)を行った方が、まだためになります。
もちろん、こうした研修が「ためになっている」と感じる方もいらっしゃると思います。
あくまで、これだけの負担を強いられている一個人の感想として、ご理解いただけると幸いです。
4. 現場の疑問:オンライン化されても高額な研修費用
ここで、現場の人間として最大の疑問を呈します。
昔はこれらの研修は、大きなホテルやホールを数日間借りて対面で行われていました。
しかし、コロナ感染予防のためにオンラインでの研修となり、現在もそのほとんどがオンライン研修に切り替わっています。
それなのに、研修費用は全く安くなっていません。
会場費や運営スタッフの人件費は大幅に削減されているはずです。 1人あたり数万円という高額な研修費用は、一体何に使われているのでしょうか?
これだけ多くのケアマネジャーが負担を感じているという現場の声は、介護支援専門員協会に届いているのでしょうか。費用の使途についても、もう少し透明性が高まると、私たち現場の人間も納得しやすいのですが…。
これでは、スキルアップという本来の目的よりも、ただ高額な費用と時間をかけて研修をこなすことが目的化してしまっているように感じられても仕方ありません。
まるで、研修を受けることが、かえって現場の負担を増やす結果になっているのではないか、とさえ思えてしまいます。
まとめ:このままでは、介護の相談相手がいなくなる
介護支援専門員(ケアマネ)は、介護が必要になった方やご家族の「最初の相談相手」となる、非常に重要な専門職です。
しかし、その上位資格である主任ケアマネの取得と維持に、これだけの時間的・金銭的・精神的な負担がかかっているのが、今の日本の「リアル」です。
(ようやく国もこの負担を減らそうと動き出し、先日も協議会で話し合い、決定された事の報道がありましたが、新たな研修制度の増設の意見もあり、現場の感覚とはまだ開きがありますね。)
このままでは、ケアマネの「なり手」がいなくなります。
将来、私たちが老後を迎え、介護の相談をしたくても「相談できる相手がいない」という大変な状況が、すぐそこまで来ているのかもしれません。
今回は専門的な話になりましたが、介護業界のこんなリアルも知っていただけたら幸いです。