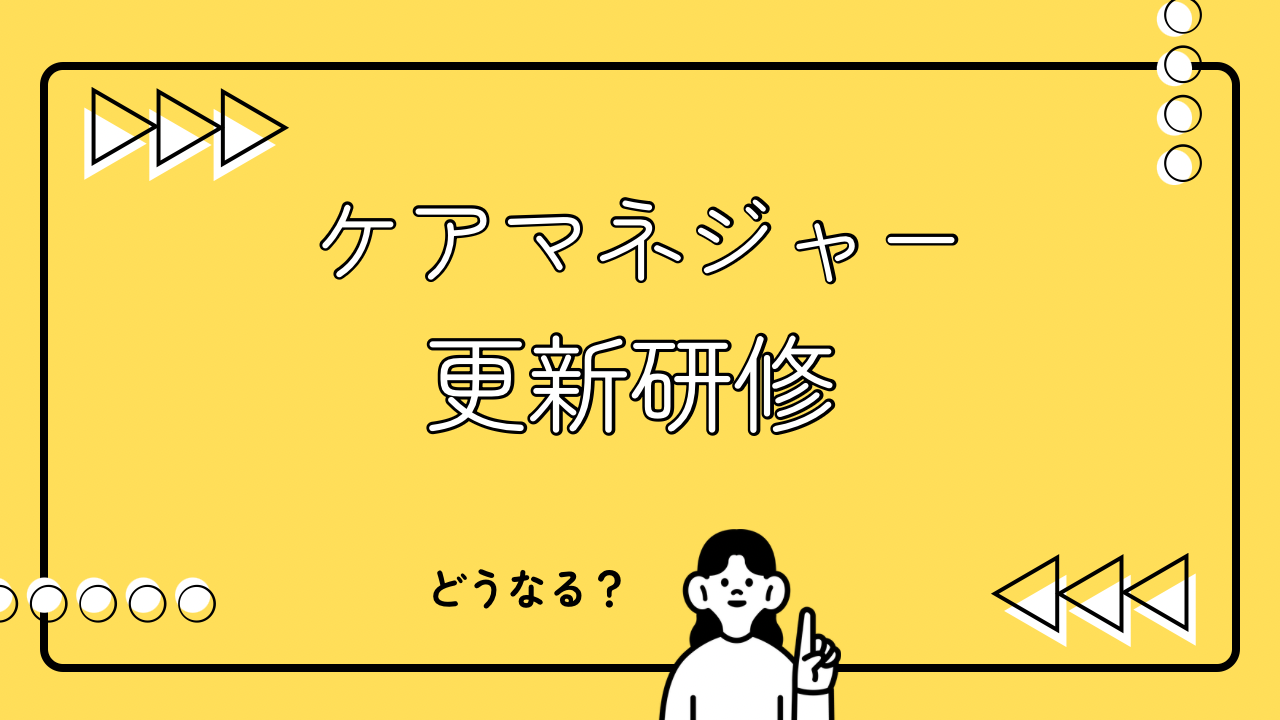介護保険サービスの”かなめ”とも言えるケアマネジャー(介護支援専門員)。
利用者の状況に合わせてケアプランを作成し、サービス事業者との調整を行うなど、その役割はますます重要になっています。
私もケアマネジャーとして仕事をしており、その一人です。
しかし今、ケアマネジャーを取り巻く環境は厳しさを増しています。
高齢化が進み、医療ニーズの高い方や認知症の方、一人暮らしの方、老々介護と、より複雑な課題を抱える方が増え、ケアマネジャーに求められる役割は拡大しています。
その一方で、ケアマネジャーのなり手は伸び悩み、むしろ減少傾向にあるという課題も抱えています。
このままでは、将来的にケアマネジャーが不足し、必要な支援を必要な人に届けられなくなることも懸念されます。
こうした状況を受け、現在、厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会では、ケアマネジャーが専門性を十分に発揮し、質の高いケアマネジメントを提供し続けられるよう、制度の見直しに関する議論が進められています。
本日開催される部会(第127回)では、特にケアマネジャーの資格更新制度 と 法定研修 のあり方が大きな論点となるようです。
現在、ケアマネジャーの資格は5年ごとの更新制で、更新のためには研修を受ける必要があります。
この研修が厄介で、時間もお金もかかってしまい、業務をしながら研修を受けるだけでも負担がかかりますが、その上少しでも遅刻するようであれば更新することもできず、業務ができなくなるのです。
給料をもらう仕事のために、この体験を5年後としなければならず、家庭を持つ身にはリスクがありすぎます。
ケアマネジャーの成り手が減少するわけですよね。
この仕組みについて、現場からは様々な声が上がっていました。
今回は、この更新制と法定研修の見直しに関する議論を中心に、ケアマネジャー制度が今後どのように変わっていく可能性があるのか、資料をもとに分かりやすく解説します。
なぜ見直しが必要?
- 更新制・法定研修の現状と課題
- ケアマネジャーの更新制度と法定研修は、専門職としての知識や技術を維持・向上させるために、平成18年度から導入されました 。定期的に研修を受けることで、変化する制度や新たなケア技術に対応し、ケアマネジメントの質を担保することを目的としています。
しかし、この更新制と研修について、現場のケアマネジャーからは負担が大きいという声が多く聞かれます 。
- 時間的・経済的負担
研修時間: 現行の更新研修(2回目以降)は32時間 。主任ケアマネの更新研修は46時間 と、決して短くありません。
日常業務が多忙な中で、研修時間を確保するのは容易ではありません。
受講日程の制約: 研修は決められた日程で集中的に行われることが多く、「研修を1回でも休んだら更新できない」というプレッシャーを感じているケアマネジャーが約8割もいるという調査結果もあります 。
受講費用: 受講料が高額であると感じているケアマネジャーが約7割にのぼります 。都道府県によって費用は異なりますが、数万円かかることが一般的です。
地域医療介護総合確保基金による補助がある場合もありますが、限定的です。
移動時間・費用: 研修会場までの移動時間や交通費も負担となります 。オンライン研修も増えていますが、環境整備に費用がかかるとの声もあります。
- 研修内容・質への疑問
「演習の時間が長すぎる」と感じる人が約半数います 。
「講師の質に問題がある」「習得すべき知識・技術が含まれていない」「内容が地域の実情に合っていない」といった意見もそれぞれ約3割あります 。
「2回目以降の更新で同じ内容を何度も受講しなくてはならない」ことに疑問を感じる人も半数以上います。
- 更新制そのものへの疑問
研修の意義は認めつつも、「資格更新の条件とすべきではない」と考えるケアマネジャーが約6割にのぼります。
「特に意味はないが決まりだから仕方なく受講する」と考えている人も約3割いるのが現状です 。
これらの負担感は、ケアマネジャーの離職の一因となっている可能性も指摘されており、人材確保の観点からも見直しが急務とされています。日本介護支援専門員協会も、研修の重要性は認めつつ、更新制は廃止し、研修受講義務とは切り離すべきとの意見を提出しています。
どう変わる? 更新制・研修見直しの方向性(案)
今回の部会資料では、これらの課題を踏まえ、以下のような見直しの方向性が示されました。
- 更新制の廃止
研修受講を要件とした5年ごとの資格更新の仕組みは 廃止 する方向で検討されています 。これは主任ケアマネジャーも同様です。
これにより、「研修を受けないと資格が失効してしまう」というプレッシャーはなくなります。
- 定期的な研修受講義務は維持
更新制は廃止するものの、専門職として知識・技術を維持・向上させる必要性は変わらないため、定期的な研修の受講 は引き続き求められる方向です。
ただし、更新と紐づかなくなるため、受講できなかった場合に直ちに資格を失うことはなくなります 。
ケアマネジャーとして働いていない期間は研修が免除され、再就職する際に改めて研修を受ける、といった仕組みも想定されています。
- 研修内容・時間数の見直し
ケアマネジャーが利用者支援に使う時間を増やす観点から、研修時間、特に講義部分については、可能な限り縮減する方向で検討されています。
都道府県が実施する研修内容の改善も検討されます。
- 受講方法の柔軟化
例えば、5年間といった一定期間内に、分割して受講 できるようにするなど、ケアマネジャーが都合に合わせて柔軟に受講できる環境整備が検討されています。
- 研修受講を担保する仕組み
ケアマネジャーを雇用する事業者に対し、所属するケアマネジャーが研修を受けられるよう、必要な配慮を求める ことが検討されています。
また、ケアマネジャー本人に対しても、研修受講を促すための何らかの措置が検討される可能性があります。(現行の研修受講命令などを参考に)
その他の関連する議論
今回の部会では、更新制・研修以外にも、ケアマネジャーを取り巻く課題解決に向けた議論が行われました。
資格取得要件の見直し: より多くの人がケアマネジャーを目指せるよう、受験資格を持つ国家資格の範囲を拡大する案(診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士、公認心理師を追加)や、必要な実務経験年数を現行の5年から3年に短縮する案が検討されています。
業務の在り方の整理: ケアプランデータ連携システムなどのICT活用を推進し、ケアプラン作成や事務作業の効率化を図ります。
また、ケアマネジャーが行っている「シャドウワーク」(法定外業務)については、地域ケア会議などを活用して地域全体の課題として捉え、解決策を探る方向性が示されています。これにより、ケアマネジャーが本来のケアマネジメント業務に集中できる環境を目指します。
ここはどう改善されるのか疑問視されます。そんな簡単に決まることができないほど、ケアマネの何でも屋化は進んでいます…
主任ケアマネジャーの位置付け明確化: 後輩ケアマネジャーへの指導・助言や、関係機関との連携調整といった重要な役割を担う主任ケアマネジャーについて、その役割・業務を法令上も明確化し、その専門性を十分に発揮できる環境を整えることが検討されています。
まとめ
ケアマネジャーの更新制・法定研修の見直しは、現場の負担軽減、人材確保、そしてケアマネジメントの質の向上という、介護保険制度の持続可能性に関わる重要なテーマです。私も大歓迎です。
今回の議論では、「更新制の廃止」と「研修受講義務は維持しつつ、内容・時間・方法を柔軟化・効率化する」という大きな方向性が示されました。これが実現すれば、ケアマネジャーは過度な負担を感じることなく、専門性の維持・向上に必要な研修を受けられるようになるかもしれません。
もちろん、これはまだ検討段階の案であり、今後さらに議論が深められていきます。ケアマネジャーが専門性を活き活きと発揮し、利用者に質の高い支援を提供し続けられる制度となるよう、今後の動向に注目していきましょう。